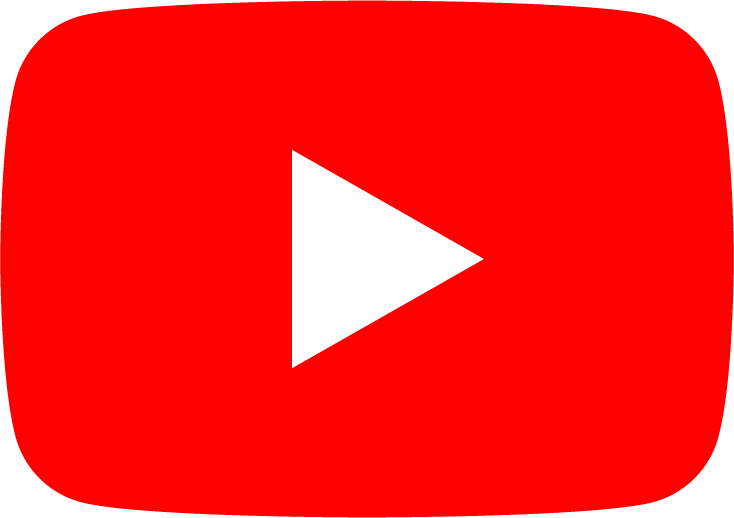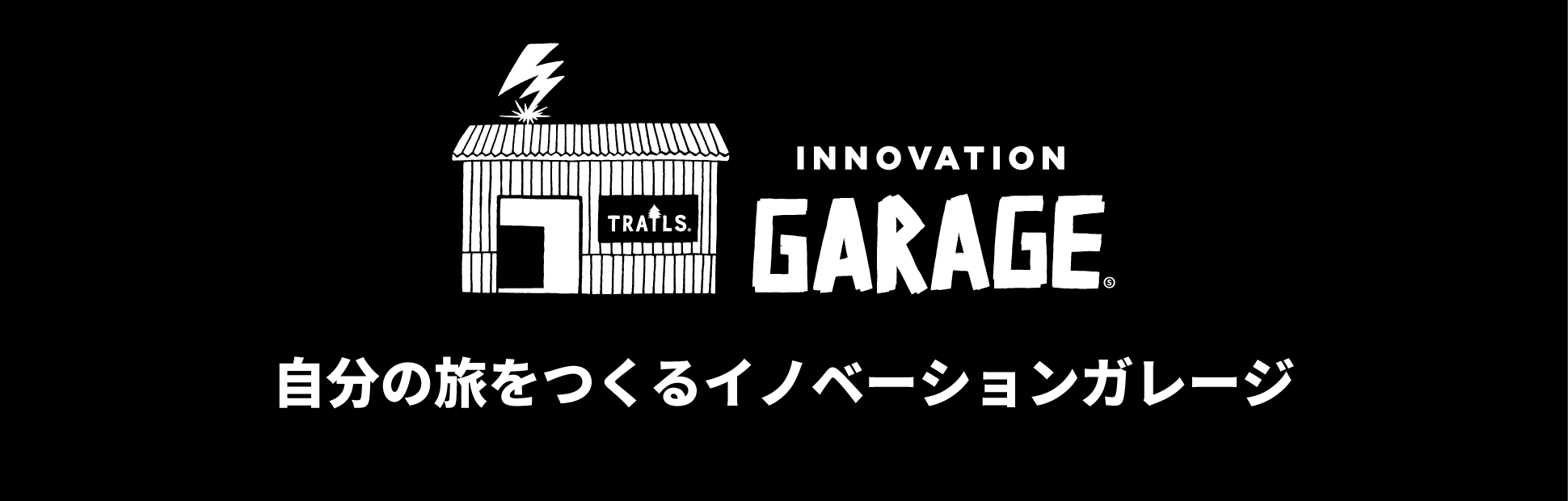パックラフト・アディクト | #21 ロシアのパックラフトの旅 <後編>川と湖をつないで白海へ

(English follows after this page.)
文・写真:コンスタンティン・グリドネフスキー 訳:齊藤瑠夏、神長倉佑 構成:TRAILS
HIKE VENTRESのコンスタンティンによる、連載記事『ロシアの旅』。ついにフィナーレです。
前回の6日目〜8日目の日中までは、次々に現れる急流に立ち向かい、パックラフトの底に穴を開けながらも、幾多の試練をなんとか乗り越えてきました。
この最終回では、念願だった白海(ロシア北西部に位置するバレンツ海の湾)にたどり着きます。
ハプニング続きのこれまでとは異なり、のんびりとキャンプしたり、村を散策したりと、それぞれが旅のラストをじっくり味わうかのようなストーリーになっています。
11日間にわたるパックラフティング・トリップはどんな終わりを迎えるのでしょうか?

ロシアのカレリア共和国でのパックラフティング。行程は、エンゴゼロ〜クゼマまでの11日間。今回の完結編は、白海〜クゼマ村までDAY8〜DAY11のトリップレポート。
ついに、バレンツ海の湾、白海にたどり着く(DAY8)
最後の最後に、私たちは白海に到着しました。しかし、その頃には干潮のピークで、舟を漕ぐのに充分な水位はもう望めませんでした。まだ残っていた海水はとても透明で、小さな貝殻や海藻が見えました。
ふと、私は水草の上いるヒトデを見つけ、手に取ってみました。この生き物をこんなに間近で見るのは初めてでした。水から出されてもなお水草を握りしめて食べ続ける軟体動物に私はとても魅力を感じました。
海にでると、みんな少しリラックスした気分でした。イルはお気に入りの態勢を取りました。それは足を投げ出し、上半身は半分起こした状態で、私もそれにならうことにしました。
私たちがあらかじめ知っていた良いキャンプ場に滞在していた時、やや泥酔していて馴れ馴れしすぎる、上半身裸の男たちに遭遇しました。
彼らは自分たちについて話したがり、真夜中に地元の漁船船長に連れてこられたこと、今年はもう魚がいなくてもうすぐ帰る予定であることを熱心に語りました。また彼らは私たちのパックラフトのことや、その費用について聞いてきました。
「彼らのような人を信用していない」とシャシュクがつぶやきました。彼はこう続けました。「彼らには何も期待できない。今はそんな人たちが周りにいてほしくない。だから、私たちがここを離れて、別の場所を探そう」。
私たちはその提案に従うことにしました。別の場所を探していると、大きな花崗岩の上にあるとても乾燥している良い場所を見つけました。でもテントを張るにはスペースが限られていて、私たちはテント同士の間隔をあける必要がありました。
また、すべてのギアを引き上げるのも困難で、かといって無人で放置する気にもなれませんでした。ただ、景色は素晴らしく、テーブルとファイアーリング付きの小さなキッチンがありました。

素晴らしい夕焼けと穏やかな気候だったので、テントの外で寝ることにした。
荷解きが済んだころには、辺りはもうすっかり真っ暗でした。私はイルに「みんなテント無しで外に眠ったらどうだろう?」と提案すると、イルは賛成してくれました。この暖かい夜、私たちはこんな風に過ごしていたのです。
水の補給と浄水に苦労した、最後の休息日(DAY9)
この日は、この旅3度目の、そして最後の休みの日でした。かなり早い段階で、私たちは飲料水が足りなくなることに気がついていたので、仲間が探検したり、魚釣りをしたり、リラックスしている間、ドブルシャとイルマールと私は水を探しに行きました。あのキャンプ場にあったメッセージに書かれていた井戸、もしくは水源を探すことにしたのです。
たぶん、水のある島は、私たちがいた場所のすぐ後ろの島だと考えました。その時は満潮だったため水位が5m以上も上がっていて、私たちが立っていた岩がかなり小さく見えました。
私たちは舟に飛び乗って、岬のまわりを漕ぎ進み、Kalostrov(カロストロフ)島にたどり着きました。遠くからでもその島がすでに使われていることは見てとれていたのですが、実際に上陸すると3世代からなるモスクワからの大家族がいることが分かりました。彼らは、すでに1カ月間にわたって島を巡っていたこと、それが彼らの夏休みの過ごし方であること、を私たちに教えてくれました。
「ここに井戸のようなものがあると耳にしたのですが」と、私たちは彼らに尋ねました。「そのことについて何かご存知ですか?」と訊くと、幸運なことに、彼らは知っていました。「でも、それは本物の井戸ではありません。ただ地面に掘った、泥水しか集められないような穴です。しかも、今ではほぼ干からびています」。
「あなたたちはどこで新鮮な水を調達しているのですか?」と私は聞きました。「私たちは雨水を集めています」。そう言って彼らは彼らのキッチンの上のタープを指さしました。「雨がない時は、水たまりを使います。この島の反対側の、トロリーバス(電気を動力として走るバス)の近くに大きいのがありますよ」。
「今なんて?」「すぐに分かるよ」そんなやり取りをしながら笑う彼らは、泥水でいっぱいの「井戸」の方向を指しました。

モスクワからの家族がトロリーバスと呼んでいたミニバンを発見。
「彼らの言う通り、水たまりを試してみよう」と納得した私たちは、彼らが「トロリーバス」と呼んでいたであろう島の場所にパックラフトを担いでいきました。そこへ行ってみてわかったのは、それが簡易ベッド付きの一時的な避難所に改装した、ミニバンの一部であることでした。
「どうやってここまでたどり着いたのか?」私たちは疑問に思いました。ミニバンの中で見つけた、ラミネートされた小さな地図がこの質問の答えを教えてくれました。
冬場、この島のまわりの水は凍りつき、氷上を運転することが可能なのです。「トロリーバス」の隣には、細かく切られた木の幹がありました。1つには穴が開けられていて、フライパンで料理するために必要な火をおこすのに完璧なものでした。それは、私たちが戦利品として持ち帰るのに充分な価値を持っていました。
そこからさほど遠くない場所で、私たちは水筒を満杯にさせるのに充分な量の水のある水たまりをいくつか見つけました。私たちはろ過装置を持っていなかった(旅の前にみんなで相談して、必要ではないと置いてきた)ので、キャンプ場に着いて即席のろ過装置を作る必要がありました。
そのろ過装置は、一方は底を切り落とした、2つのプラスチック製のボトルからできていて、中に苔を詰めて、砕いた石炭も入れ、衣服の一部も使いました。さらに、水はすべて一度煮沸してから飲むことにしました(美味しくはありませんでしたが、何もないよりはマシです)。
この日、Pongoma(ポンゴマ)村(白海から一番近い集落)より遠くへは行かないという決断もしました。この決断により、予定よりも6km短い総距離で済むことがわかりました。
この距離は、向かい風の中で漕げば、長い間海上にいなければならなかったかもしれない距離でもありました。ここで私たちは、村の代表として振舞っているが、彼女の電話番号からしてモスクワに住んでいたであろう女性と連絡を取りました。彼女には、私たちが電車に乗らなければいけない、クゼマという場所までの送迎を手配してもらうことになりました。
その時、サウナを持っている人を知っているか彼女に尋ねたところ、彼女は見つけ出すと約束してくれました。会話を交わし終えた数分後には、サウナの持ち主の電話番号を連絡してくれました。また、以前はここら辺に店があったが、週末は早く閉まってしまうから気をつけるようにと私たちに教えてくれました。
あと少しで終わる私たちの旅を祝うために、その晩は豪華なごちそうを食べました。予定していたスープの他にも、他の島から持ってきたくぼみのある木を使って作ったパンケーキを食べて、キャンプ地のそばにある干潟で集めたムール貝を煮ました。
泥だらけになりながら、島に上陸(DAY10)
一晩で天気ががらりと変わりました。曇りがちな天気で、私たちがラフトに乗り込む時には雨が降ってきました。これまでの旅で蓄積された疲れと、最終目的地までわずか数十kmだという事実は、私たちを急かしました。
そして、そんな時は必ずしも最適な選択ができないということを、私個人としても、はっきりと肌で感じました。
ほとんどの冒険はこの言葉から始まると言われます。「心配ない、私は近道を知っているから」。
それはまさに、Kalostrov(カロストロフ)島についた時に私が発した言葉でした。そこは干潟だったため、本土へと繋がる細い道ができていました。「その上を歩こう、島をまわっていくよりも短距離のはずだ」。私は、前を一緒に歩いていた人たちにそのように提案しました。
そして、私たちはパックラフトを運び始めましたが、泥だらけになってしまうことに気づいたのです。「あと数mでパドルを漕ぐことができるよ」。そう言って、私はみんなを励ましました。
しかし、そううまくはいかず、その先には充分な水がなく、厚くて粘着性のある泥が、歩くのもほぼ不可能な状態にしていました。もう戻るのは遅すぎて、一歩踏み出すごとに、脚を引っぱりあげながら前進しなければなりませんでした。
風向きも変わり、風に沿って舟を進めていたのが風を避けながらパドルを漕がなくてはいけませんでした。水上で約4時間が過ぎた頃、私たちはポンゴマ川の河口と村のあるShangostrov(シャンゴストロフ)島に到着しました。
すべての準備は明日のためにされていたので、私たちは最終日の夜はその島に滞在することにしました。しかし、まず、私たちは新鮮な水と食料を確保する必要がありました。前日に計画していたよりも少し多めに食べてしまい、水たまりの水も使い果たしていたのです。
なので、他の人たちがキャンプの準備をしている間に、レフとシャシュクは村までパドルを漕いでいきました。約1時間後、彼らは悪い知らせと共に戻ってきました。私たちが紹介されていた店は完全に閉店していたのです。
井戸(モスクワからの女性が電話で教えてくれた井戸)を見つけることもできなかったので、彼らは、泥酔しているような老夫婦に水について訪ねてみました。老夫婦は川の向こうを指さしました。「満潮の時にしなければいけないんですが」と彼らは教えてくれました。「そうしないと、水が少し塩辛くなってしまうのです」。
私たちはこの老夫婦の情報を完璧に信じたわけではありませんでした。でも、今は選り好みしている場合ではありませんし、飲み水に困っている今、ドブルシャはパドルを漕いで川を上り、私たちの分まで水筒を満杯にしてくる役目を買って出てくれました。
しかし、彼が充分に遠くまで行かなかったからか、はたまた水を汲んだタイミングが悪かったからか、その水は「少し塩辛い」ものでした。
私たちは、最後に残っているティーバッグで美味しくて温かいお茶を作ろうとしました。
最初に試したヴァディムは「これはまずい」と言い、他のみんなも「自分も飲みたくない」と言いました。
このような、飲めない水をどうすればいいのかと考え、これでスープを作ることにしてみました。「どうせ塩を入れるのだから、初めから塩辛い水を使ってみるのはどうか」と思いついたのです。そして実際に作ってみると、とても美味しいスープが完成しました。
夜が近づいてきたころ、Byelorus(バイロルス)から来た、複数のソビエト式カヤックに乗った大規模なグループが到着しました。彼らのリーダーは私たちの隣でキャンプをしていいかと尋ね、私たちはいいと答えました。
おそらく、私たちが拒否しても意味はなかったと思いますが、それでも、このときに断っておけばよかったと後になって思うのです。私たち全員が眠りにつきかかった頃、その隣人たちは夜中、ずっと大きな声で騒いでいたのでした。
クゼマ村にたどり着き、村の中を歩きまわる(DAY11)
翌日、喉の渇きと催眠不足による疲れのなか、私たちはパックラフトをたたみ、最後の500mしかない長旅を始めました。村はもっと内陸にあったのですが、私たちが腰をおろしたのは大きな倉庫で、そこは捕った魚を貯蔵しておくために使われていたもののようでした。昔はとても景気のいい産業でしたが、今はほぼ放棄された状態です。
村自体は、古くて老朽化した家々と新しく改装された建物とが混ざり合ったようなところでした。新しく綺麗な家々の隣に駐車されていた車のナンバープレートからすると、その住人のほとんどがサンクトペテルブルクからの人々でした。
私たちは「衛星放送受信アンテナがついているレンガ造りの家」を探していました。少なくとも、それがその家主が電話で説明した特徴でした。「岸から歩いてくると見つかりますよ」と、彼女は言いました。
実際に、その条件に合う家は少なく、私たちはその家を簡単に見つけ出せました。近くには、煙突から煙の出ている、比較的大きな薪焼のサウナがありました。「これは私たちのためのものに違いない」私たちはそう思い、家から出てきた50代の小柄な男性に近づきました。前歯のない彼はヴァシリーという名前でした。
ヴァシリーは私たちを待っていてくれました。「クゼマの店まで私たちを連れて行ってもらえませんか?」と訊くと、「問題ありません。片道で200ルーブルになります」。にっこり笑いながら彼はそう言いました(200ルーブルはたったの3ユーロ以下)。

村人のヴァシリーが、このラーダ7で僕たちを店まで連れていってくれた。
全員ではいけなかったので、彼はレフと私を車に乗るように促しました。古いラーダ7で、ナンバープレートは付いていませんでした。
私がなんとなくシートベルトを締めようとした時、彼は笑って「心配はいらない」と言い、こう続けました。「私はここを時速40km以上で運転することはできません」。町へ行く途中、彼はこの道が以前は鉄道の道として使われていたけれど、70年代に壊されたことを教えてくれました。
11日間の旅の終わりと、仲間たちとの別れ(DAY11)
私たちが村について聞いた時、夏だけ外からやってくる人たちを除くと、80人がその村に住んでいて、そのうちたった2人(彼ともう1人)だけが職を持っているのだと彼は言いました。「だけれど、ここで職のない彼らはどうやってかウォッカのためのお金を見つけてくるのです。私は本当に彼らがどうやっているのか分からない」。
彼は鉄道のために働いていましたが、それは季節限定です。夏にはいつも魚釣りに行ったり、狩りをしたり、ベリー摘みをしたりしています。彼の奥さんも仕事がなく、「ここで女性が仕事を探すのは、ほぼ不可能です」と彼はつぶやきました。
「8月終盤のパドリング・シーズンが終わった後、狩猟の季節が始まります」。「ここにはどんな動物が生息しているのですか?」「ムース、ヘラジカ、冬にはトナカイもいます。ここにはライチョウとガチョウもいます」「危険な動物もいるのですか?」「はい。クマもいますし、冬にはトナカイを捕まえにオオカミもやってきます。でも、やはりクマが多いですね」と、このような会話を交わしました。
でも恐れる必要はありません。クマは人をとても警戒していて、決して人に寄りつきません。「もし寄りつけば、クマは人に捕らえられるでしょう」彼は何かを思い出して笑いました。
「私の隣人は漁網を確認しに行ったときに、魚に引き寄せられたクマに出くわしました。彼はボートでクマから逃げようとしたのですが、逆に、ボートにぶつかったクマが逃げだしたのです」。そして私たちは笑いがこみ上げてきました。「もちろん、クマを殺すの簡単ではありません。ムースやヘラジカとは違いますから」。
レフと私は、彼が言おうとしていることがよくわからないまま、お互いを見つめました。その様子を見たヴァシリーは、島から島へ泳ぐヘラジカを見つけたら、通常は角にイカリを引っかけて、ヘラジカが溺れるまで引っ張るのだと説明しました。
「しかし、イカリが底に着くと、あなたとあなたのボートが転覆してしまいます。だから、ヘラジカを引っ張るときは岸から離れすぎてしまわないように気を付けなければなりません」。ヴァシリーの話を聞くのは、まるで違う世界から来た人の話を聞いているようでした。
このあたりは自然豊かですが、苦労も多かったのです。「車のガソリンを買うには、80km以上も運転しなければいけないことを知っているでしょう」。彼は私たちに言いました。
サウナへ戻り、先に楽しんでいたみんなと合流しました。ドブルシャはお風呂に関して詳しく、シャシュクは彼のカイロプラクターのスキルを活かしてみんなの背中の整体をしました。
体を清潔にし、休息を取り、お互いに別れを告げるときが来てしまいました。レフとヴァディムと私は、その日の遅い電車に乗らなければなりませんでしたが、他のみんなは翌朝にオリョール(ロシアにあるみんなの地元)へ戻るようでした。
私たちはわかれる前にハグを交わし合いました。それは素晴らしい旅で、全員の心が浮いたり沈んだりしながらも、私たちは最初から最後まで楽しむことが出来ました。
「さあ、来年はヨーロッパのどのあたりに行こうか?」
(English follows after this page)
(英語の原文は次ページに掲載しています)
関連記事

パックラフト・アディクト | #20 ロシアのパックラフトの旅 <後編>次々と現れる急流に挑む

パックラフト・アディクト | #14 ロシアのパックラフトの旅 <中編>たび重なる困難と幸せなキャンプ生活
- « 前へ
- 1 / 2
- 次へ »
TAGS:




























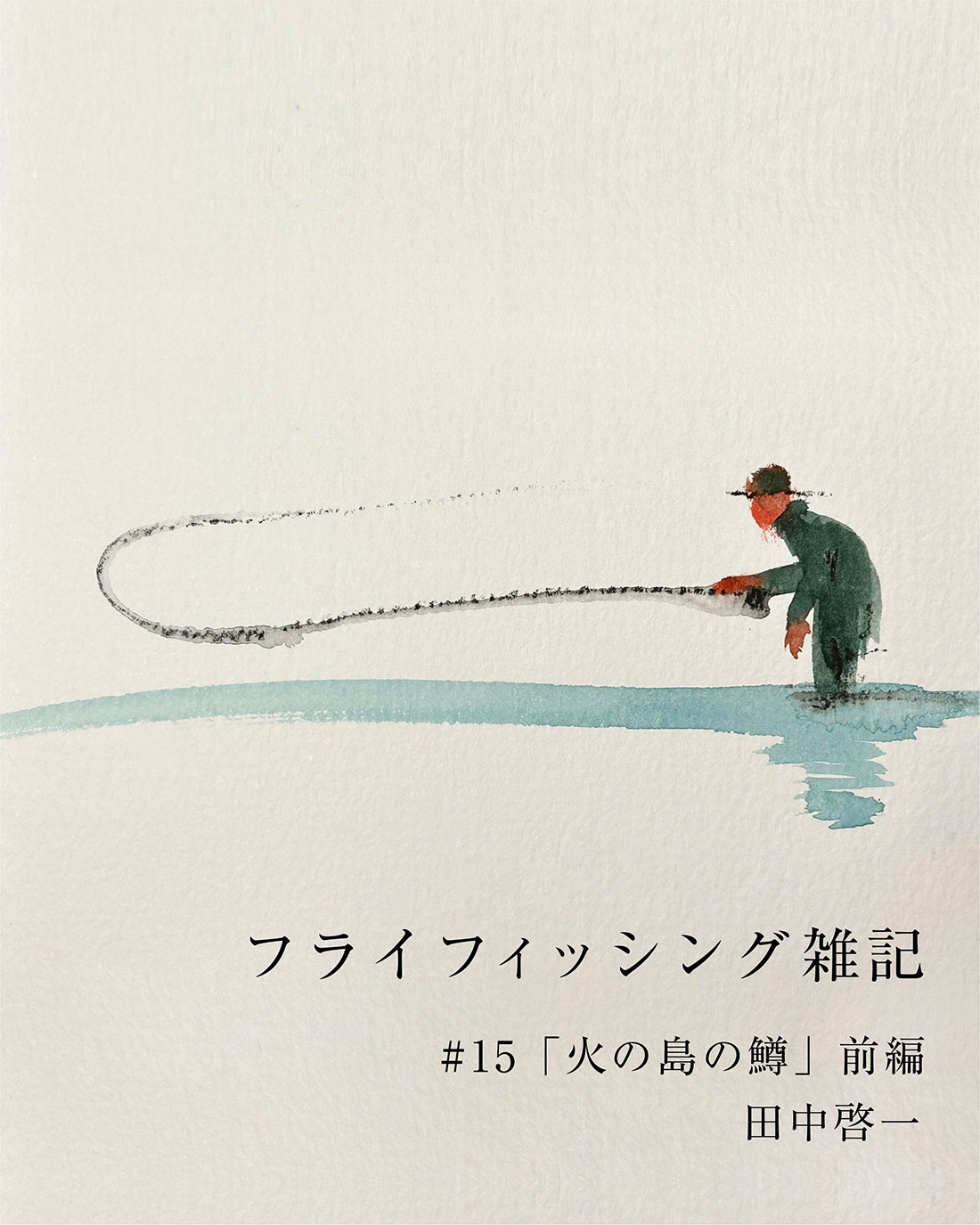
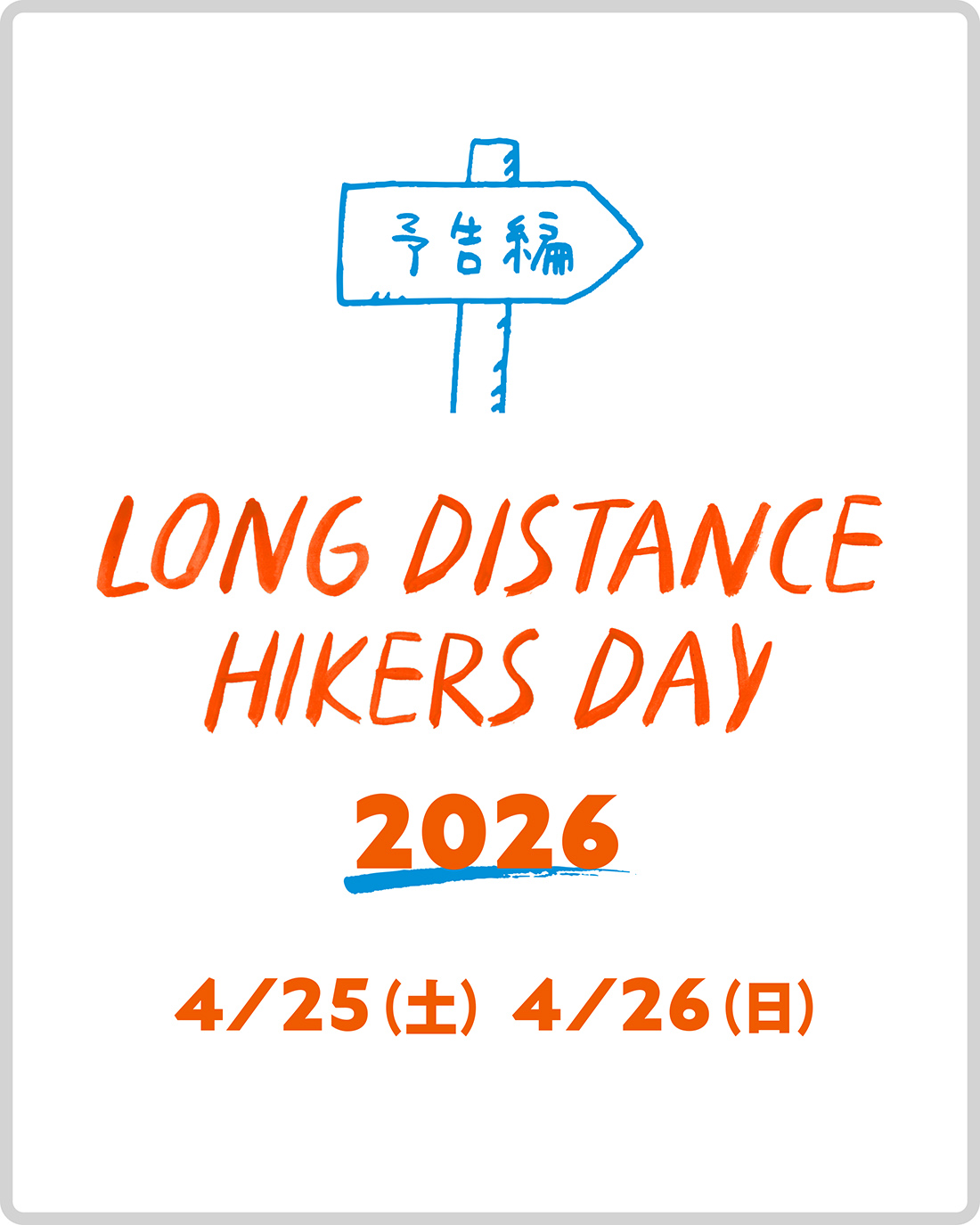

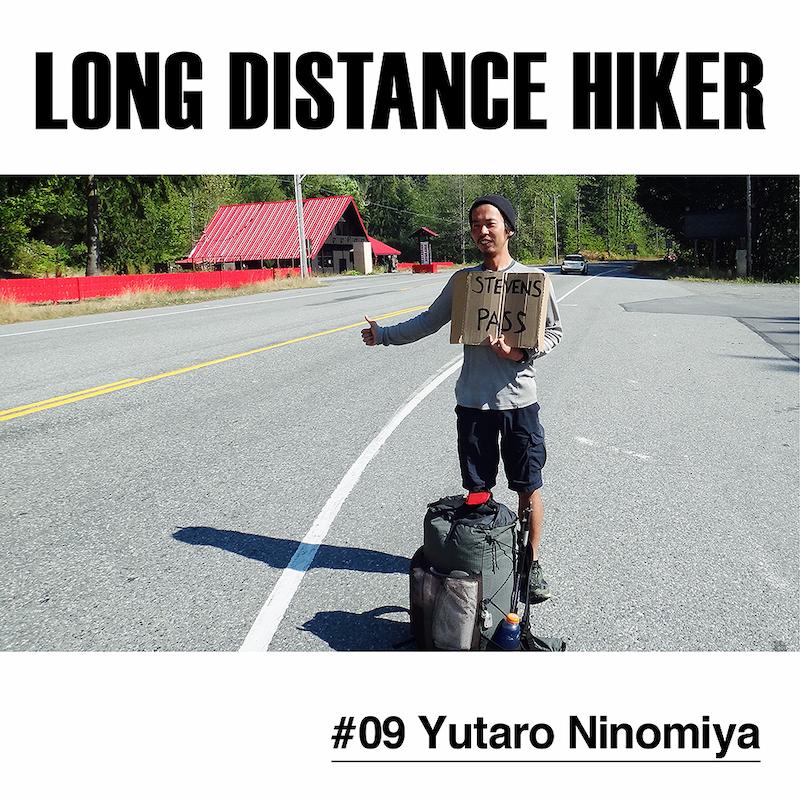




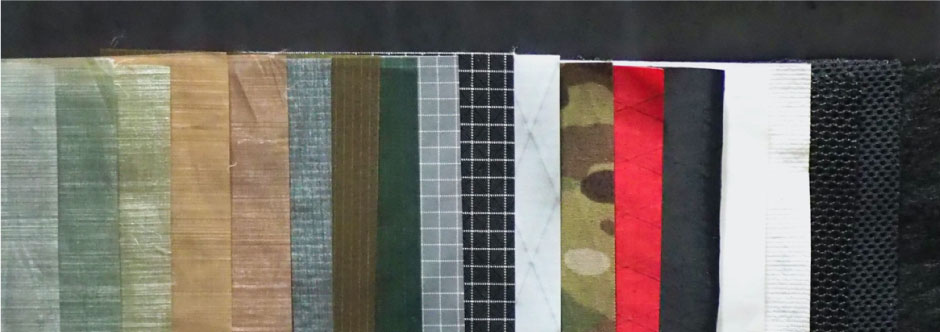
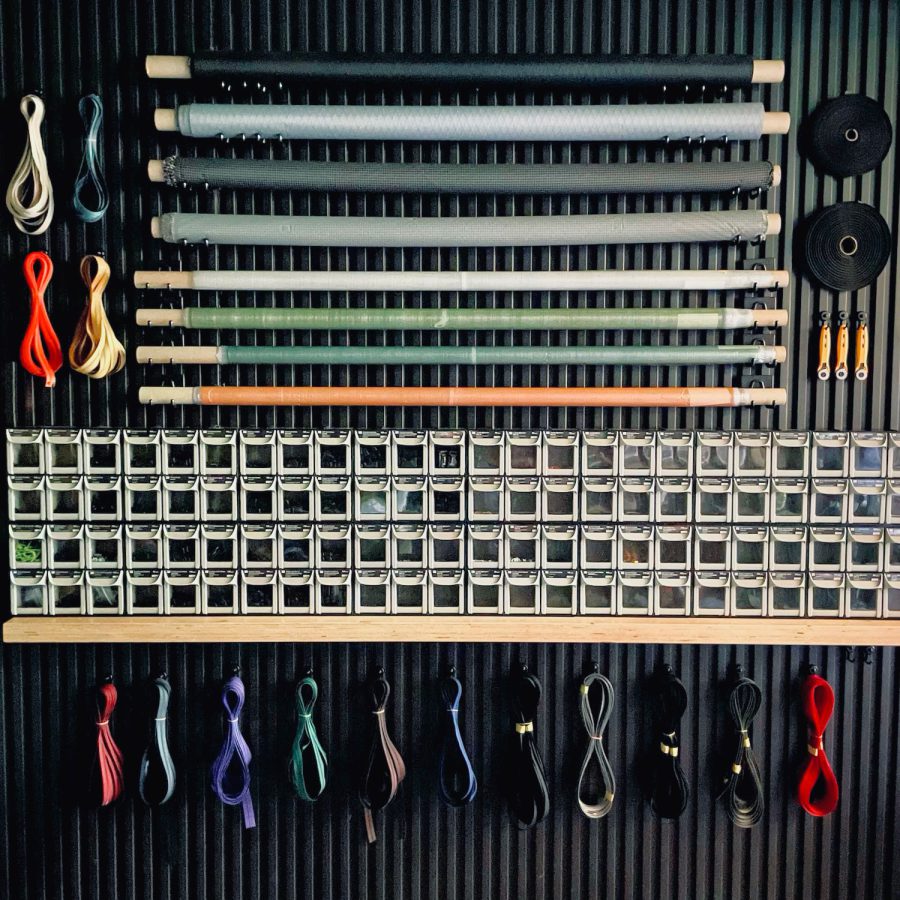 ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…
ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)
Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)
Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…
Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…
Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …
Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …
Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …
Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…
Tenkara USA | Tenkara Lev…